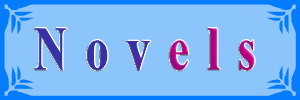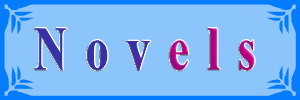ある日のことである。我が最愛の妻がこんなことを尋ねてきた。
「ねぇ、あなた知ってる? 幻獣王の持ってる小さな包みのこと」
「あぁ、知ってるが、それがどうしたんだ?」
「その小さな包みの中身を見たことある?」
「いや、見たことはないが。どうしてそんなことを聞くんだ?」
「いえ、いいの。見たことがないのならいいの」
妻は特にゴシップネタが好きではないし、そもそもドラゴンは、自分以外のドラゴンに干渉するのは好きではない。いやそうでもないか。ドラゴンは、惚れた相手の気を引く為には、思いっきり自分をアピールするし、相手に関してはどんなささいなことでも知りたがるしなぁ。
そうそう、私も最愛の妻をGETするために、どれだけ苦労したことか。
はっ!まさか!妻が浮気を?しかも相手は幻獣王?まだ私達は新婚だというのに。
いや、そんなはずはない。幻獣王はまだまだ発情期も迎えていない若者だ。
私以上に彼女を大切にしている家庭もそうはいないぞ、たぶん。
しかし最近、多くの若い雌ドラゴンが、成長を早めている幻獣王の気を
ひこうとコナをかけているという噂も聞いているし。
なぜ彼女が幻獣王の持つ小さな包みなんかを気にしているんだろう?
ああ、とても気になる・・・。このままじゃあ、今夜は眠れないかも・・・。
「どうしたの、あなた?急に難しい顔しちゃって」
心配そうな顔で声をかけてきた妻。私のことを心配してくれているのか?
「あ、いや。なんでもない」
しまった。今、どうして幻獣王の包みのことを尋ねたのか聞けば良かった。
「なんでもないって顔じゃないわね。どうしたの? 私には言えないことなの?」
いかん。やっぱり気になる。ええぃ、聞いてしまえ!
「なあ、どうして君は幻獣王の小さな包みが気になるんだ?」
「んー。ちょっと気になる話を聞いちゃったのよねー」
長く美しい首を少し傾げて、彼女は答える。
「なんだ? もったいぶらずに教えてくれないか? 気になるじゃないか」
ちょっと拗ねた口調で尋ねてしまう。
「そう?」
妻はクスリと笑う。彼女の笑顔に私は弱い。過去この笑顔に何度、話を誤魔化されてしまっただろう、いや、しかしここでちゃんと聞いておかないと、私の夫としての威厳が・・・・。
「どんな話を聞いたんだい?」
「おとなりのお嬢ちゃんがね」
しつこく尋ねる私に、彼女もやっと話をしてくれる気になったようだ。
お隣といっても、我々ドラゴンのお隣というのは、山2つ向こうとか、森3つ向こうという範囲である。
「ああ、君の友人のお嬢さんだね。確か、今年で20歳くらいだったかな?」
「ええ、そう。そのまだまだ可愛い盛りのお嬢ちゃんが、幻獣王の持ってる包みのことを聞いてきたのよ」
「そのお嬢さんは、幻獣王に逢ったことがあるのか?」
「たぶん逢ったことはないと思うわ」
「おかしいじゃないか。逢ったこともないのに、なぜ幻獣王が包みを持っていることを知っているんだ?」
「きっと誰かから聞いたんでしょ?」
そうかもしれない。幻獣王に逢ったことのあるドラゴンであれば、彼が常に持っている包みのことは知っているはずだ。
「まぁ、そうだろうな。でも君が気になったのは、幻獣王が包みを持っていることを、お嬢ちゃんが知っていたことだけなのか?」
「それだけなら気にならないわね」
「じゃあ、一体何を気にしているんだい?」
「気になったのはね」
「うん?」
「幻獣王の持つ包みには、私たちドラゴンを即座に倒してしまうような強力な魔法が入ってるらしい。って彼女が言ったことなのよ」
「まさか!そんなものは子供のヨタ話だろう?」
ドラゴンを即座に倒す魔法など聞いたこともない。
「子供たちの間では結構、この話が広がっているらしいの」
大人のドラゴンはそんなヨタ話を信じることはないだろう。しかし、いくら相手が子供でもその噂はまずいんじゃないだろうか?
「だから君は包みの中身を私が見たことがあるか尋ねたんだね?」
すまない・・・一瞬でも君が浮気しようとしてるなんて疑った私を許してくれ・・・と心の中で妻に詫びる。
「ええ、もしあなたが見たことあるのなら、噂はデマだってことがわかると思って」
ということは、妻は噂を信じてるってことなのか?
「君はその噂を信じるのかい?」
私の問いに彼女は笑って答えた。
「勿論、信じてはいないわ。でも、あなたは絶対に包みの中身を見せてもらおうなんて思わないでね」
やっぱり信じているんじゃないか、と私は心の中にだけ呟く。
「しかし、噂を否定するためには、誰かが確認しないと」
どうやら子供だけでなく、大人のドラゴンまで噂を信じる可能性があると知った私は、幻獣王の持つ包みの中身を確かめなければいけないのではないか?という気になってきた。
「だめよ。もし噂が本当なら、あなた死んじゃうかもしれないじゃない。あなたなしで私が生きていけると思ってるの?そんなに早く私を未亡竜にしたいわけ?」
妻の本気の言葉に、私は彼女から深く愛されていることを実感する。
「わかった。君の言うとおりにしよう。愛してるよ奥さん。しかし、噂をこのまま放置しておくのはまずいな。どうしたらいいと思う?」
「そうね。何も幻獣王に直接包みの中身を見せてもらわなくても、噂を流した超本人を探し出して否定させればいいんじゃないかしら?」
さすが、我が妻。賢い君を選んで私は本当に幸せだよ。
「そうだね。安全でナイスなアイデアだ。それじゃあ、ちょっと隣のお嬢ちゃんに誰からその噂を聞いたのか確かめに行ってみよう」
妻と私は早速、お隣さんの家に向かって飛び立った。
「こんにちは。シィちゃん」
我々ドラゴンは滅多にフルネームで相手を呼ばない。
ゆえに「シィちゃん」はお隣のお嬢ちゃんの愛称である。
「あ、火竜のお姉ちゃんだ!こんにちは。今、ママはお出かけしてていないの」
火竜のお姉ちゃんというのは、火の魔法を得意にしている我が妻のことだ。
若くて美人だから、結婚していてもお姉ちゃんと呼ばれて当たり前である。
「こちらのおじちゃんは?」
このくそガキめ〜!私は妻とそんなに年は離れてないぞ!
妻がお姉ちゃんなのに、私はおじちゃんと呼ばれて不機嫌になる。
「いいのよ。今日はシィちゃんに聞きたいことがあってきたの。それとね、こちらの<お兄さん>はお姉ちゃんのダーリンなのよ。覚えておいてね」
「ごめんなさい。お兄さん、初めまして。お姉ちゃんにはいつもママがお世話になっています」
デキたお嬢ちゃんじゃないか!とたんにお嬢ちゃんが可愛く見えてくるとは現金なものだな、私も(笑)。
「こちらこそだ。ところでシィちゃん。ちょっと聞いてもいいかな?」
「なあに?」
「シィちゃんは幻獣王の持ってる包みの話を誰から聞いたのかな?」
「うーんとね、隣のマーくん」
「ありがとうね、シィちゃん。さぁどうしましょう、あなた?」
ここの隣は山2つ向こうか・・・そんなに遠くないな。
「私が行ってくるよ。君は家に帰って待っていてくれるかい?」
「わかったわ。じゃあ気をつけて。早く帰ってきてね」
所詮は子供たちに広がった噂だ、遊び仲間に聞いたというのならたかが子供たちの家の範囲、そう遠くまで行くこともないだろう。
「じゃあ、行ってくる」
妻とお嬢ちゃんの見送りを背に、私は隣のマーくんの家に向かった。
「息子ですか?さっきお隣のナギちゃんの家に遊びに行くって出かけたばかりなんですが」
マーくんは友達の家に遊びに行って不在だった。
「うちの息子が何か悪さでもしたんでしょうか?」
心配気な顔で尋ねる母親に、私はあわてて答える。
「いえ、少しお聞きしたいことがありまして。幻獣王の持っている包みの噂はご存知ですか?」
「まあ、その話ですか。とんでもない話ですよね。勿論、私は信じてませんよ。でも、もし噂が本当なら、幻獣王は何を考えていらっしゃるんでしょうねぇ?」
やはり、この母親も噂を半分は信じているんじゃないか・・・
「そうですよね。ドラゴンを倒す魔法なんて、そうそうあるもんじゃないですよね?」
「え?ドラゴンを倒す魔法ですか?そんな話になってるんですか?
おかしいわねぇ。私は包みの中身を見るとドラゴンが病気になるって聞いたんですが」
「ドラゴンが病気・・・。つまり病気になって倒れるってことなんでしょうか?」
「うちの息子は噂ををナギちゃんから教えて貰ったと聞きましたが」
「そうですか、すみませんが、そのナギちゃんの家はどちらか教えていただけますか?」
マーくんの母親は親切にナギちゃんの家を教えてくれたので、そそくさと礼を言って、私はナギちゃんの家に向かった。
教えてもらった家は、マーくんの家から森ひとつ向こうにあった。
家の前で2頭のチビ竜が遊んでいる。きっとあれがマーくんとナギちゃんだろう。遊んでいる子供たちに近寄ろうとしたその時、私の周囲を囲むように炎の壁が出現した。
「オイオイ・・・」
ありがたいことに私には火霊の加護があるので、炎の壁は苦もなく通りぬけることが出来るのだが。
炎の壁を通り抜けて近づいてきた私に、2頭のチビ竜は警戒心を顕わに聞いてきた。
「オジサン、誰?」
「竜さらいじゃないでしょうね?」
ム、ムカツク〜!このクソ生意気なチビ竜どもめ!
オジサンだとっ! 私はまだ若いんだ。さっきのシィちゃんといい、このガキどもといい!しかも竜さらいだと? この私のどこが竜さらいに見えるんだ? 私はそんなに悪竜ヅラをしているというのか?失礼な!
心の中では散々、文句をいいつつも、私は子供相手に怒鳴るほど冷静さを失っていなかったので、静かに子供たちに尋ねた。
「君はマーくん、そしてお嬢ちゃんはナギちゃんかな?」
「・・・・」
「・・・・」
チビ竜たちは答えない。お嬢ちゃん(たぶんナギちゃん)が口を開いた。
「相手に名前を聞く前に、自分の名前を名乗るのが礼儀だとパパに聞いたわ」
ドラゴンはそう簡単に名前は名乗らないんだけどなぁ、しかも私は君たちの名前を知ってるんだけどなぁ。
「私はシィちゃんにマーくんのお家を聞いて、マーくんのお母さんにマーくんがナギちゃんのお家に遊びに行ったと聞いてきたんだが。まあいい、私の名前は・・・」
「久しぶりだな、赤の谷の若旦那」
「パパ!」
背後からの声に振り向くと、顔見知りの竜が近づいてきた。
「なんだ、君の娘さんだったのか」
「ああ。若旦那にはまだ会わせたことがなかったな。俺の可愛い娘ナギだ。おぅ!マーくん来てたのか、いつもナギを守ってくれてありがとうな。彼はつい先日、赤の谷のマドンナと結婚してラブラブハッピーな新婚生活を送っている赤の谷の若旦那だ。さ、二人とも挨拶しなさい」
「初めまして、赤の谷の若旦那さん。さっきは炎で囲んじゃってごめんなさい。僕、ナギちゃんを守らないといけないと思って」とマーくん。
「マーくんを怒らないで。私からも謝ります。初めまして、私ナギです」とナギちゃん。
「怒ったりはしないよ。しかしマーくん、その若旦那さんって言うのはやめてくれないか」
「ハハハ、まあいいじゃないか?さっきはマーくんの炎の防御壁で出迎えちまって、すまなかったな。最近、変態なドラゴンがいると聞いてな。どうやら可愛いドラゴンをさらう奴らしいんだが、そいつは火霊の加護がないらしいから、念のためだ」
「そうか、子供を持つ親ってのは大変だな」
「若旦那も、じきに子供を持てば、心配するようになるさ」
「いや、私のところはまだ当分・・・妻と私だけの生活を楽しもうと・・・」
「まいったな、そいつはノロケってもんだ。ところで、若旦那がここまで来たのは何かあったのか?」
私はここまでの経緯をかいつまんで説明する。
「ふ〜ん。幻獣王の持ってる包みねぇ。そんな大層なものが入ってるとは信じられんな。なぁ、ナギ、おまえ誰にその話を聞いたんだ?パパに教えてくれるかい?」
「えっとねぇ、赤の谷のタクちゃん」
「だとさ、若旦那。知らなかったのかい?」
赤の谷のタクちゃんとは、私の腹違いの兄の息子、つまり私の甥である。
灯台下暗しの言葉が私の頭の中をこだました。
「あぁ、私は今、妻と赤の谷を出て暮らしているからな。全く知らなかった」
「ハネムーン状態ってわけだ」
「赤の谷では、妻の元求婚者たちからのやっかみが強くてねぇ」
「それは赤の谷のマドンナをかっさらった若旦那の宿命だね。少々のやっかみは仕方ないんじゃないの?そんじゃまあ、タクちゃんに真相を確かめてみるんだな」
「勿論そのつもりだ。それじゃあこれから赤の谷に行くとするか」
「マドンナにもよろしくな」
「わかった。ありがとう。マーくん、ナギちゃんも元気でな」
「さよーならぁー」「バイバーイ」
とチビ竜たりの声を背に私は実家のある赤の谷に向かった。
たくさんのドラゴンが住む集落がある。集落の中に赤い谷があるから、赤の谷と呼ばれている集落である。自分でいうのもなんだが、赤の谷での私の人気は高い。
「お帰りなさい、若旦那」
「おーい、若旦那のお帰りだー」
「お久しぶりです、若旦那」
「きゃぁぁあ、若旦那のお帰りだわ、ラッキー」
顔を合わせるドラゴンが、次から次へとわらわらと挨拶をしてくるが、そんなものに時間をかけてはいられないので、挨拶もそこそこに兄の家に向かう。赤の谷に住む長老が私の父親であり、赤の谷の旦那と呼ばれている私の兄と私はかなり年が離れている。
妻と赤の谷を出てから、しばらくこちらには帰ってくるつもりはなかったのだが。
「久しぶりだな。よく帰ってきた」
ウッ、いきなり兄さんと顔を合わせてしまうとは。私は兄さんが苦手なんだ。小さい頃、兄さんにいじめられた等の事実は全くない。ただなんとなく兄さんの前では緊張してしまうんだなぁ、これが。
「ご無沙汰いたしております、兄さん」
「うむ。奥方はご壮健か?」
「ええ、元気です。義姉さんもお元気ですか?」
「あぁ、家内は元気だが。どうした? 滅多に帰ってこないお前が、こちらに戻ってくるということは何かあったのか?」
「いえ、ご心配をおかけするようなことは何も。ところで兄さん、タクはいますか?」
「なんだ、タクに用なのか?さっきまで近くで遊んでいたんだがな」
「じゃあ、探してきます」
「タクにどんな用があるんだ?」
やはり聞かれるだろうな・・・と思っていた私は、さらりと流す。
「たいした用じゃないんです。少し聞きたいことがあるだけですので、それでは失礼します」
「まあいいだろう、今度は奥方も一緒に顔を見せなさい」
「わかりました。すみません、兄さん」
私に聞いても無駄だと察したのか、兄もそれ以上の追及はしなかった。
後でタクが兄さんに絞られようと知ったこっちゃない。
さっきまで近くにいたというだけあって、まもなくタクを見つける。
「あ、おじちゃんだー!いつ帰ってきたのー?」
今日おじちゃんと呼ばれたのは3回めだ。まあタクからみれば、私はおじさんであってるんだが。
「こら!タクッ!おじちゃんじゃない、私のことはお兄ちゃんと呼びなさいと前に言っただろう?」
「わかったよぉ。お帰りなさい、お兄ちゃん。お姉ちゃんは?」
「お姉ちゃんは今日は家でお留守番だ」
「えぇ?なんでぇ、僕、お姉ちゃんに会いたかったのにぃ」
「わかった、わかった。今度はお姉ちゃんも連れて帰ってくるからさ」
「本当ー!わーい!わーい!」
喜んで羽根をパタパタさせるタクに、改まった口調で尋ねる。
「なぁ。タク、お前さぁ。幻獣王の持つ包みの話を誰から聞いた?」
「・・・・・」
騒いでいたタクの口がピタリと止まる。
「なぁ、タク。もう一度聞くが、誰から聞いたんだ?」
タクは目に涙を溜めて、私を見上げる。
「お兄ちゃん、怒ってるの?」
「いや。怒ってないよ、タク。お兄ちゃんは、タクが誰から話を聞いたのか教えて欲しいだけなんだ」
「パパに言わない?」
「わかった。言わない。約束する」
「本当に?」
「絶対に言わない」
私が言わなくても兄はきっとタク自身に説明を求めるだろう。
「・・・・の・・・ちゃん」
「何だって?」
タクの声が小さくて聞こえない。
「げ・・・のお・・ちゃん」
「タク、聞こえないよ」
「幻獣王のお兄ちゃん」
大衝撃(メガショック)!そんな馬鹿な。まさか幻獣王本人が噂を流したというのか?
「タク、幻獣王に会ったのか?」
「うん・・・」
「どこで?」
「ナギちゃん家の近くの森」
「いつ?」
「1カ月くらい前」
「どうして幻獣王に会った?」
タクはポツリポツリと話はじめた。
両親に内緒でナギちゃんの家に遊びに行く途中、森で急に大きな風とともに現れた大きなドラゴンに襲われかけたこと。身がすくんで魔法を唱えられずに、助けを求めたときに、漆黒のドラゴンが現れて助けてくれたこと。
確かに兄さんに内緒で遊びに行って襲われたなんて言えんな。
「それで助けてくれたドラゴンは幻獣王と名乗ったのか?」
「あんなドラゴンは放置しておけない、今にきっと退治するから、待っていてくれと言われたから、僕・・・聞いたんだ。あなたは幻獣王陛下ですかって?」
「それで?」
「そしたらにっこりと笑って、陛下ではなくて、兄ちゃんでいいって」
ドラゴンがドラゴンを退治するなんて約束できるのは、確かに幻獣王だろう。彼は無愛想な表情が多いが、子供には笑うこともあるんだ・・・と私はひそかに驚く。
「なるほど。たぶん間違いないな。彼は幻獣王だろう。それで、タクはどうして包みの話を聞いたんだ?」
「助けてくれた後にね、お兄ちゃんがなんだか大切そうに小さな包みを持ってたから、その包みは何ですか?って聞いたんだ」
「チャレンジャーだな、タク・・・」
幻獣王に面と向かって質問できるガキなんて、かなり大物かも、こいつ。
「そしたらね。お兄ちゃんが言ったんだ」
「なんて言ったんだ?」
ここからが肝心だな。
「この中身は見せられない。お兄ちゃんは、この中身を見ると、ドキドキして、身体が熱くなって、そのうちボーッとして中身のこと以外は考えられなくなるんだって。だからお兄ちゃん以外のドラゴンには見せられないって言ったんだ」
「それで、タクはナギちゃんに、幻獣王の持っている包みの中を見ると病気になると説明したわけだ」
「うん」
なるほど、幻獣王も幻獣王だ。紛らわしい説明を・・・。見せたくないなら素直に見せたくないと言えばいいものを。
「わかった。タクの説明は間違ってない」
「パパには絶対言わないでね」
「ああ、約束だから、私は言わないよ。じゃあ私はそろそろ帰るから。
それとタク」
「何?」
「遊びに行く時は、ちゃんと出かける先をパパかママに言っておきなさい。
でないと、何かあった時に、いつも誰かが助けてくれるわけじゃないんだから」
「わかった・・・」
「約束するか?」
「うん、約束する」
「それじゃあな、またな」
なんとなく、幻獣王の持つ包みの中身がわかってきたような気がする。大体の噂の真相がつかめてきた私は、噂はやはりデマだったと説明するために、私の帰りを待つ妻の元へ帰路を急いだ。
ある日のことだ。一人の長老が俺を呼び止めた。
「幻獣王殿」
「なんだ?」
「お礼を申し上げます」
「何の話だ?」
「森で我が孫を不埒者から助けてくださったとか」
あぁ、あの時の。あの子は長老の孫だったのか。
「いや、当然のことをしたまでだ」
「しかしドラゴンの子供をさらうドラゴンがいるとは忌々しきことですな」
「そうだな。変態は徹底的に叩きのめさないと、罪のない民が迷惑を被ることが多いからな」
「ごもっともです」
「どうやら陰界にはまだ変態なヤツがいるらしいから、注意するように長老からもみんなに伝えておいてくれ」
「わかりました」
長老がまだ何か言いたそうな表情をしているのを見て、ウランボルグは尋ねる。
「まだ、何かあるのか?」
「幻獣王殿、王たるもの、嘘をつくことはいけません」
「どういうことだ? 俺がいつ嘘をついたんだ?」
「幻獣王殿がいつも大切にお持ちの小さな包みのことを、我々はよく存知ておりますが」
「それがどうかしたのか?」
「巷の子供が申しますには『幻獣王殿はドラゴンを即座に倒してしまう魔法を包みの中に持っている』と」
「そんな馬鹿な!俺はそんなことを一言も言った覚えはないぞ」
長老の言葉にウランボルグは驚きを隠せない。
「またある子供は『包みの中を見るとドラゴンですら病気になる』と」
長老のその言葉で、ウランボルグは自分が包みを見せる断りの説明で失敗したことを悟る。
「すまない、長老。俺は彼に紛らわしい説明をしてしまったんだな」
「息子から孫が陛下に助けられたことを聞きましてな。
まあ子供の間でそのような噂が流れているとなると、さすがにまずいのではないかと」
「ああ、あの包みの中身についてそんな噂が流れるとは思ってもみなかった」
さすがのウランボルグも反省することしきりである。
「ところで、幻獣王殿はどのように中身を説明されたわけですか?」
長老からの問いかけにウランボルグは苦笑して答える。
「この中身を見ると、ドキドキして、身体が熱くなる。そのうちボーッとして中身のこと以外は考えられなくなると」
長老はウランボルグの説明を聞いて渋い顔をする。
「確かにそれは病気の説明と勘違いされても仕方ありませんな」
「噂を否定するためにはどうすればいい?力を貸してくれないか?」
さすがに、子供達の間で不穏な噂を流しておくのは、幻獣王として見逃すことは出来ない。
しばしの間、考え込んでいた長老はウランボルグに提案する。
「幻獣王殿、その包みの中身を公開されてはいかがか?」
「それはイヤだ。断る」
「なぜ、お断りになられるのか?」
「これは俺の宝だ」
「幻獣王ともあろう方が物に執着されるのか?」
「これを公開すると欲しいと思うヤツが出てくるにちがいない」
「ドラゴンはあまり他のドラゴンの物に執着しないと思いますが」
「これだけは別だ」
「では中身が何かお尋ねしてよろしいか?」
「・・・・」
答えないウランボルグに、長老は苦笑してなだめるように言い聞かせる。
「公開はしない、中身が何かもわからない・・・では噂は否定できません、幻獣王殿」
「わかった」
ウランボルグは大切に持っていた小さな包みを長老の目の前に置く。
「長老には見せる。だが他のドラゴンには見せないでくれ」
差し出された包みをそっと開けて、長老は嘆息する。
「なるほど、わかりました。幻獣王殿の説明は子供には誤解されても仕方ありませんでしたが、こうして中身を見せていただいて納得いたしました。誰にも見せたくないという理由もわかりました。公開はやめましょう。ただし」
「ただし・・・?」
「中身が何であるかは公表させていただきます。よろしいですね?」
ウランボルグは渋々頷いた。
「なぁに、公表すれば噂などは一気に消えますよ」
そう簡単に言ってのけた長老は「眼福、眼福!」と笑顔でその場を後にした。
数日後、陰界では幻獣王の持つ包みの中身について、一大センセーションがわきおこる。ウランボルグ以外に唯一、その中身を見たことがあるという長老の元に、中身についての問い合わせが殺到することになる。
長老が発表した内容とは:
告知:幻獣王が所持する「誓約者の肖像画」はこれを非公開とする。
長老曰く「眼福!眼福!わしのような老いた竜にとっては寿命が一層伸びたような気がするわ。しかし若い竜には目の毒じゃな、あれを見ると恋の病に冒されかねんて」
それを聞いた他の長老が、ウランボルグに肖像画の公開を迫ったとか、
それにウランボルグがどう対応したのかは後日の話である。
END
2001/10/2 KARIN

|